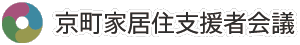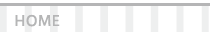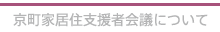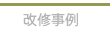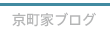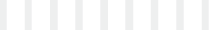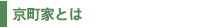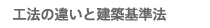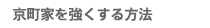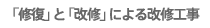京町家とは
平安京ができた頃から、居住用の建物として建てられ、連綿と受け継がれ発展してきました。
構造的には「伝統工法」と呼ばれる木組で建てられています。
柱は石の上に置かれていて、通り庭という土間空間があり、その上は吹き抜けの火袋(ひぶくろ)になっています。
継ぎ目のない長い柱が半間間隔で並んで、その屋根を支えています。
柱は貫という水平の材で繋がれ、その間の壁は竹小舞が組まれて土が塗られています。
表の通りに面して軒が通っていて、出格子、虫籠窓(むしこまど)、ばったり床几(しょうぎ)が残っていることもあります。
坪庭や天窓など、風や光を採り入れる工夫がされています。








はじめに << 京町家とは >> 工法の違いと建築基準法